2025年春、ITストラテジスト試験に合格しました。
正直、不合格だと思っていたので「驚き」と「嬉しさ」が同時に込み上げてきました。特に午後Ⅱ試験では指定の文字数に届かず、「これは落ちたかもしれない…」と感じていたからです。
それだけ ITストラテジスト試験は午後Ⅱ(論文)対策が最大の難関だと思います。本記事では、私の合格体験を「勉強法」「試験当日の様子」「合格後のメリット」までまとめました。これから受験する方の参考になれば幸いです。
試験結果

ITストラテジスト試験の概要と難易度
ITストラテジスト試験は、情報処理技術者試験の中でも最難関に位置づけられる高度区分の資格です。
特に特徴的なのは、その内容が経営戦略や超上流工程に強く関わる点です。私自身、SIerでシステムエンジニアとして働いていますが、若手の段階では業務で直接携わることが少なく、実務経験をそのまま論文テーマに活かしにくい難しさを感じました。
また、午後Ⅱの論文試験があることも大きな特徴です。単に知識を問われるのではなく、自分の経験をもとに「経営やIT戦略にどう貢献できるか」を論理的にまとめる必要があります。これが、他の高度情報処理試験と比べても一段と難しい部分だと感じました。
実際の合格率は毎年15%前後で、他の高度試験(システムアーキテクト、ネットワークスペシャリストなど)と大きな差はありません。ただし、IPAの統計情報【令和7年度公表データ】を見ると、受験者の経験年数が10年以上に偏っているのが特徴的です。合格者数(無記入除く)は経験年数20年以上が41%。つまり、社会人として長く経験を積んだ層が挑戦する試験であり、若手SEが合格するのは容易ではないといえます。
受験のきっかけと背景
私がITストラテジスト試験を受けようと思ったきっかけは、コンサルティング業務への興味でした。
システムエンジニアとしてERP導入に携わる中で、提案フェーズが身近にあり、「将来的に自分も関わることになるだろう」と考えていました。そのため、早いうちに経営や戦略に関する知識を整理し、体系的に学んでおきたいと思ったのです。
また、この資格を取得したからといって直接的に転職活動が有利になるとは考えていませんでした。経営やIT戦略を扱うこの試験の勉強を通じて、体系立った知識を得られること自体に価値があると感じていました。転職予定はないですがキャリアの選択肢として業務を理解しておきたかったです。
勉強法と使用教材
私がITストラテジスト試験に取り組んだのは 2025年2月1日から試験本番の4月20日までの約2か月半 でした。短期間でしたが、戦略的に学習を進めることで合格できました。
午前Ⅰ対策
午前Ⅰは範囲が広く暗記要素が多いため、応用情報技術者試験 過去問道場を利用しました。
- 令和6年秋期~令和3年春期までの直近8回分を選び、各回を3周ずつ繰り返し解く
- スマホでスキマ時間に演習できるため、通勤中や休憩時間にも取り組めた
午前Ⅱ対策
午前Ⅱは「ITストラテジスト試験 午前Ⅱ対策 1」というアプリを利用しました。
- 直近6回分を5周ずつ解き、知識を定着
- 4回分くらい進めると同じ問題が繰り返し出題されるため、効率よく復習できる
- こちらもスキマ時間に活用できたのが大きなメリットでした
ITストラテジスト試験 午前Ⅱ対策 1(App Store)
午後Ⅰ対策
午後Ⅰは90分で3問中2問を解答する形式です。私は TACの「ALL IN ONE パーフェクトマスター ITストラテジスト」を使用しました。
- 全13問のうち、8問を解答
- 演習から試験時間配分を徹底(3問確認5分+1問目40分+2問目40分+見直し5分)
- 本書に記載の「3段跳び法」で解答
- 設問のキーワードを拾う
- 問題文のキーワードと対応づける
- 必要な情報をもとに解答を作成する
特に「間違えた時にどうやれば正答にたどり着けたのか」を意識して復習したことで、6問目あたりから時間感覚と正答率が安定しました。
午後Ⅱ(論文)対策
午後Ⅱは120分で2問中1問を選択して解答する論文試験です。私は以下の2テーマが来ると想定し準備しました。
- テーマ1: DX対策「CRMの構築とCRMを活用した新規ソリューションとマーケティング」
実際の業務でCRMの連携システムに関わった経験をベースに構成。企業HPにある事例を参考に情報収集し、試験本番でもこのテーマを選択。論文では「社内ITストラテジスト」という立場で記述。 - テーマ2: AI対策「IoT・AI・ロボティクスを駆使したスマートファクトリー」
ゼロから構築したテーマ。AIは幅広く活用され、成果を説明しやすい分野のため選定。
書いた論文本数は2本。使用教材は「ALL IN ONE パーフェクトマスター ITストラテジスト」です。
工夫した点
- 過去問を読み込み、出題テーマと回答を抽象化して汎用的に使えるフレームを作成
- 出題テーマと回答の抽象化からChatGPTを活用して情報収集と文章作成を行った
- 情報収集では以下の観点で整理
- 事業概要(顧客、提供価値、収益構造、コスト構造など)
- 事業環境(競合や市場動向)
- 業界特性や戦略
- 文章作成では、以下の構成を頭に入れて試験に臨みました
- 事業概要と事業環境
- ITを活用した新サービスの企画内容
- 経営層への提案内容と評価
- 情報収集では以下の観点で整理
このように「テーマ選定 → 情報収集 → 論文構成」の流れで論文を作成し、試験本番でも落ち着いて取り組むことができました。
試験当日の流れと感想
当日のスケジュールと準備
前日に昼食をコンビニで購入し、パンとおにぎりを用意しました。お菓子はチョコとラムネを持参し、各休憩で糖分補給をして集中力を維持しました。当日のスケジュールは以下の通りです。
- 午前Ⅰ:9:30~10:20
- 午前Ⅱ:10:50~11:30
- 昼休憩(会場で昼食)
- 午後Ⅰ:12:30~14:00
- 午後Ⅱ:14:30~16:30
午前・午後Ⅰの手応え
午前Ⅰ・午前Ⅱ・午後Ⅰについては、想定していた通りに解けて合格レベルの手応えを感じました。教材で繰り返し演習した成果がしっかりと出たと思います。
午後Ⅱの手応えと注意点
午後Ⅱでは、準備していた「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」に関するテーマが出題されました。想定通りのテーマだったものの、「案件概要」を具体的に記述する設問があり、そこで約15分を要してしまいました。
「案件概要」は毎年記述が求められます。私は本番で初めて見て工数や人数、期間に違和感がない値を設定しなければと焦ってしまいました。皆さんは事前に準備しておきましょう。
特に「設問ウ」で指定されていた文字数に届かず、試験直後は「これは不合格だろう」と感じていました。実際、論文試験では文字数不足は大きな減点要素になり得るため、本番ではかなり不安が残りました。
それでも合格できたのは、事前に準備していたテーマ構成や内容そのものが評価されたからだと思います。これから受験される方には、時間配分を徹底することと、文字数を満たす練習を繰り返しておくことを強くおすすめします。
「設問ア」「設問イ」は多めに記載をしたため、合計の文字数は届いたことも評価対象にある可能性があると考えています。
案件概要の設問では、以下の項目が求められます。
構想、計画策定、システム開発などの名称
① 名称(30文字以内)
対象とする企業・業種
② 企業・機関などの種類・業種
③ 企業・機関などの規模(人数)
④ 対象業務の領域
システムの構成
⑤ システムの形態と規模
- クライアントサーバシステム(サーバ台数、クライアント台数)
- Webシステム(サーバ台数、クライアント台数)
- メインフレームまたはオフコン(台数)及び端末(台数)
- その他
⑥ ネットワークの範囲
- 他企業・他機関との間
- 同一企業・同一機関の複数事業所間
- 単一事業所内
- 単一部門内
- なし
- その他
⑦ システムの利用者数
構想、計画策定、システム開発などの規模
⑧ 総工数(人月)
⑨ 総額
⑩ 期間
構想、計画策定、システム開発などにおけるあなたの立場
⑪ あなたが所属する企業・機関など
⑫ あなたが担当した業務
⑬ あなたの役割
⑭ あなたが参加したチームの構成人数
⑮ あなたの担当期間
会場の雰囲気
会場の雰囲気としては、年代層は20代が2割、30代が2割、40代が4割、50代が2割程度でした。全体的に落ち着いた雰囲気で、年齢層が高めの試験であることを改めて実感しました。
合格後に感じたメリット
合格して最も大きかったのは、戦略策定・提案・推進といった業務理解が格段に深まったことです。これまで携わってきた業務はシステム導入中心でしたが、資格勉強を通して経営戦略の視点から物事を整理する習慣が身につきました。
また、今後のキャリアにおいても、システム開発だけでなく「提案や推進」に携わりたいと考えるようになり、この資格は自分の進路を後押しする強いアピール材料になりました。
これから受験する人へのアドバイス
まず強調したいのは、午後Ⅱの論文対策では必ず文章を書く練習をしておくことです。私は構成を考える練習はしたものの、実際に文章にまとめる演習をしていなかったため、本番で大幅に時間を取られてしまいました。この反省は、これから受験される方にはぜひ伝えたいポイントです。
また、「戦略策定や提案の経験がないと合格できないのでは?」と不安になる方もいると思います。しかし、私自身も未経験の部分が多かったにもかかわらず、学習を通じて知識を補い、それを論文に落とし込むことで合格できました。経験不足を勉強でカバーすることは十分可能です。
学習を継続し、自分の経験を整理しながら取り組めば、必ず合格に近づけます。ぜひ自信を持って挑戦してください。
まとめ
ITストラテジスト試験は、単なるIT資格ではなく「経営とITを結びつける力」を問う試験です。午後Ⅱの論文対策は確かに難関ですが、正しく準備し、時間配分を意識すれば必ず突破できます。
私自身、試験直後は不合格を確信していましたが、最終的には合格できました。この体験から、最後まで諦めずに取り組むことの大切さを強く感じています。
これから受験する皆さんが、この記事を通じて少しでも学びや勇気を得て、合格へ近づいていただければ嬉しいです。
使用教材
応用情報技術者試験 過去問道場
ITストラテジスト試験 午前Ⅱ対策 1(App Store)
ALL IN ONE パーフェクトマスター ITストラテジスト
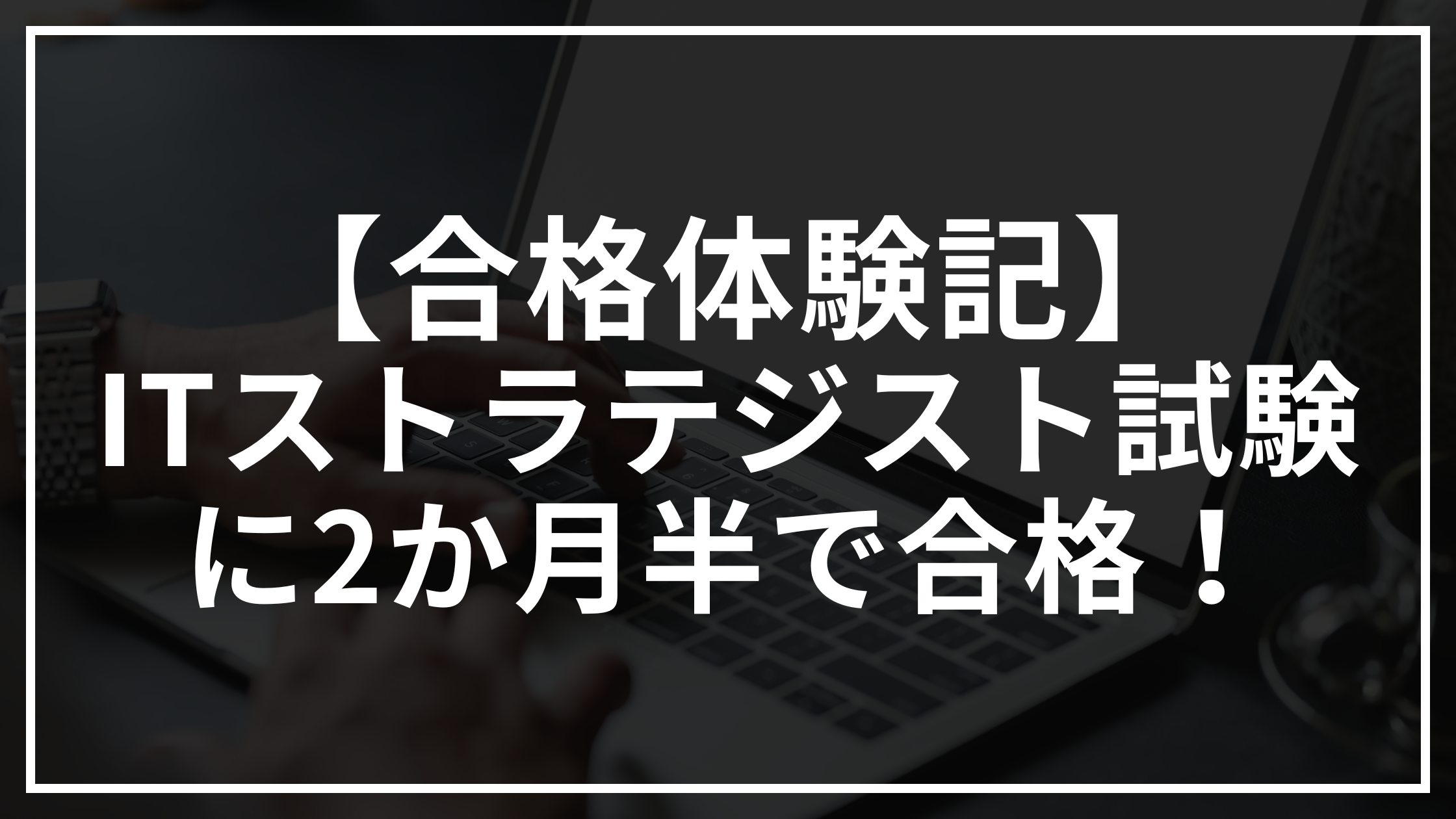
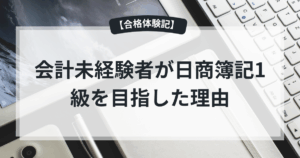
コメント